TOPICS
特集
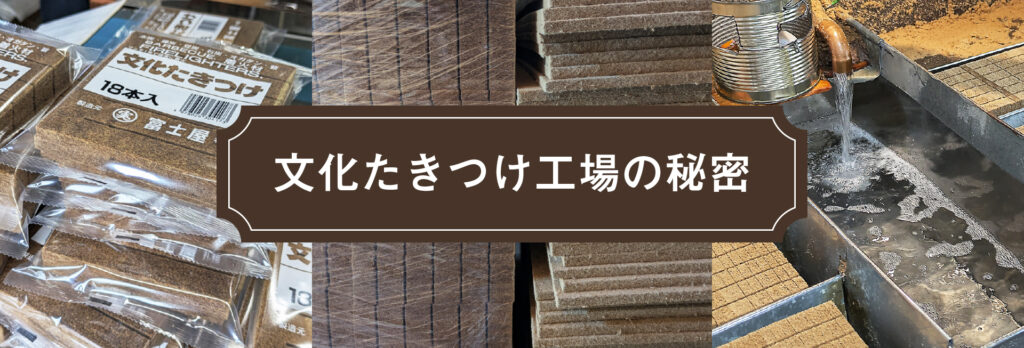
焚き火や、薪ストーブの火つけに大活躍する「文化たきつけ」を、知っていますか?
灯油を染み込ませた着火剤で、マッチ1本で手軽に火が起こせて、キャンプやBBQにも重宝します。
使っている人も多いのでは?
全国的に知名度の高い文化たきつけですが、
じつはノースイーグル誕生の地、北海道札幌にある丸実 富士屋さんの工場で作られています。
「ぶんたき」と呼ばれ、道民に愛されています。
この商品を広めたく、ノースイーグルはブンタキカンとブンタキバッグを考案。
丸実 富士屋さんにご快諾いただき、商品化できました。
さらに今回、ご厚意に甘えて、とくべつに工場見学・取材を敢行!
とってもシンプルで、使いやすく、長く愛される文化たきつけ工場の秘密に迫ります。
まずは、なかなか見られない製造工程がこちら!
工程① 材料をカット
3×6板(さぶろくばん:だいたい一畳の大きさ)の材料を、製品サイズに切り分ける。
材料の板は床材メーカーに特注している。




重ねてあると食パンみたい!
工程② 切れ目を入れる
特製のジグを使い、5本の切れ目を入れる。
手で適量を機械に押し込むので、絶妙な力加減とリズムがいる。



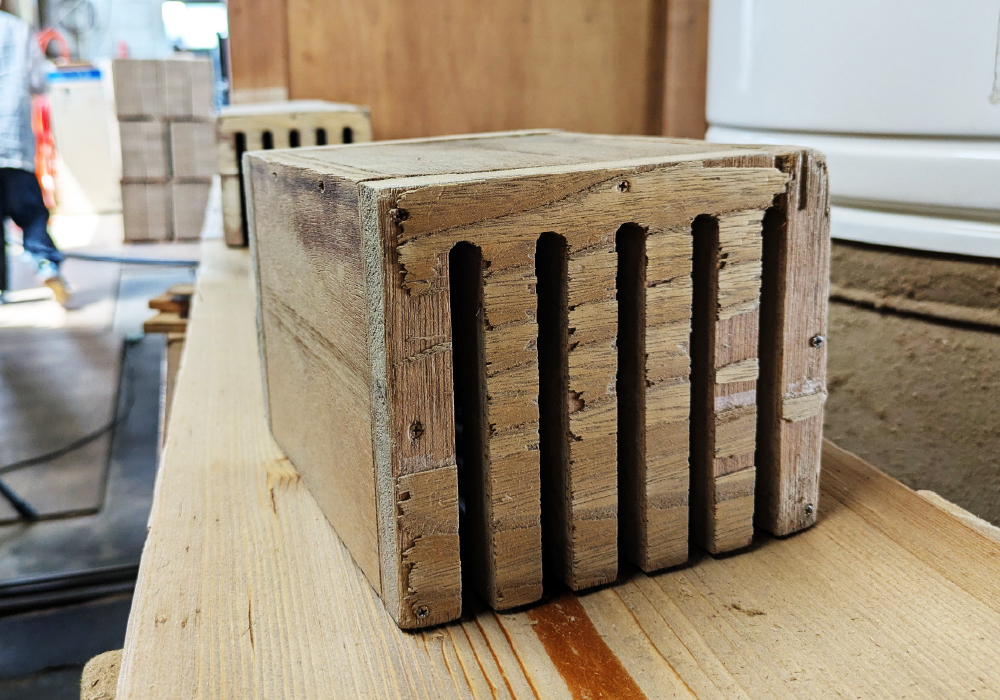
こちらが特製ジグ!
工程③ たっぷり灯油につける
おでん屋さんのような仕切りつきのバットに、灯油を流し入れ、板を入れて染み込ませる。



灯油の吸収は早く、バットに残らない!

ムラがあっても徐々に浸透していく
工程④ パッケージ
板を3枚ずつ並べ、ラインに流すと、自動でフィルムが巻かれる。
おなじみの文化たきつけのできあがり!
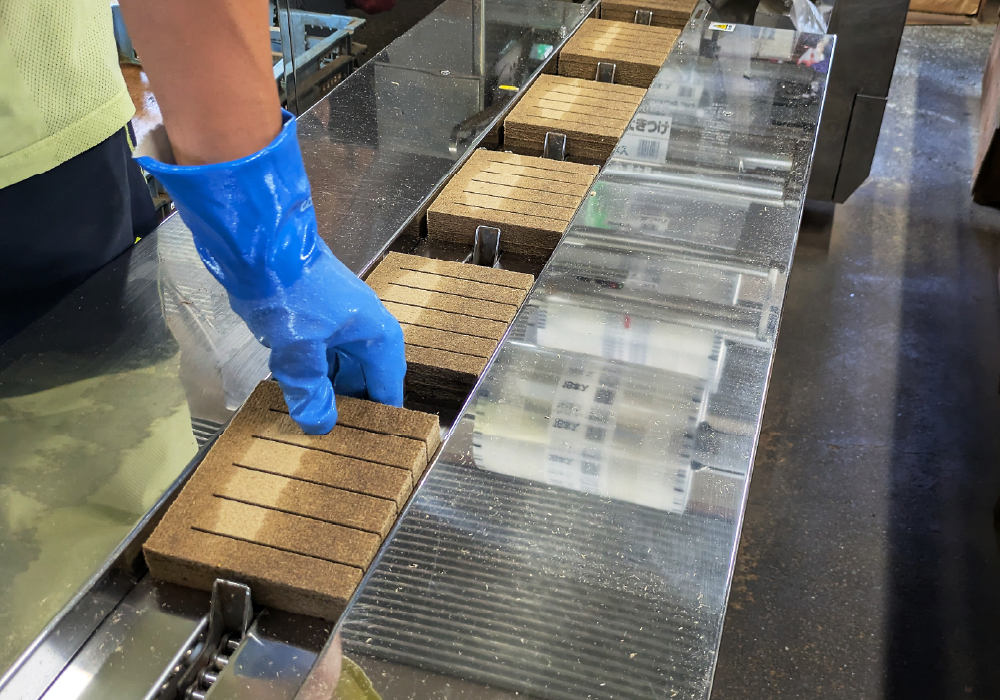



丸実 富士屋商店の中山さんにお話を聞きました!

−有限会社 丸実 富士屋商店の歴史を教えてください。
北海道札幌で1957年創業、1967年設立です。創業以来、文化たきつけの製造販売をしています。
丸実の「実」の字は創業者の名前から取っています。
−文化たきつけの名前の由来はなんですか?
創業当時、文化鍋とか、文化シャッターなど、その時代の最先端のものには「文化」をつけることが流行していたからではないかと思います。
−文化たきつけはどのように生まれたのですか?
創業者である祖父が、もともとは石炭ストーブや薪ストーブ用に作りました。
当時の北海道では、厳しい冬の暖房に石炭ストーブと薪ストーブが主流だったようですね。そこで日常的に、便利に使える着火剤として考案しました。
今では、キャンプやBBQなど、レジャーで使ってもらうことが増え、冬より夏の需要が多くなりました。おかげさまで、販売数は年々右肩上がりに増えています。



北海道の冬の暮らしを支えてきた文化たきつけ。
昔ながらの使いやすさにこだわり、この商品ひとすじで製造されています。
工場見学からは、手作業の工程が多く、ていねいに作られていることがわかりました。
丸実 富士屋商店さん、中山さん、取材にご協力いただきありがとうございました!
火つきが良く、たくさん入っている文化たきつけはコスパ良し!
だからこそ一度で使いきれず、残ることも…
そこで、ブンタキカン・ブンタキバッグの出番です。

ブンタキカン ¥880(税込)
文化たきつけ保管用のブリキカン。メイドインジャパンのきれいな四角缶で、こまごましたキャンプ用品を整理したり、おうちで小物入れにするのもおすすめ。
ブンタキカン NE40009 商品ページ
ブンタキバッグ ¥550(税込)
文化たきつけ保管用のジッパーつきバッグ。中身に合わせてトップをロールダウンすればコンパクトに。マッチやライターを一緒に入れるのも便利。
ブンタキバッグ NE40010 商品ページ
どちらもインナーバッグつき!
使い方は、使いかけの文化たきつけを入れたら、口元をロールダウンし、お手持ちの輪ゴムで止める。そのあとカンやバッグへ入れる。インナーとして使うことで、さらに匂いもれや乾燥、湿気を防ぐ。




みなさんも文化たきつけを使って、BBQや焚き火を楽しんでくださいね。
【解説】文化たきつけ
木材繊維に灯油を染み込ませた着火剤。1パック18個入り。6片に割れるブロックが3枚入っている。必要な分をその都度割って使え、継ぎ足しやすいのも魅力。
サイズ:約130×30×150mm 重量:約270g(当社調べ)

















